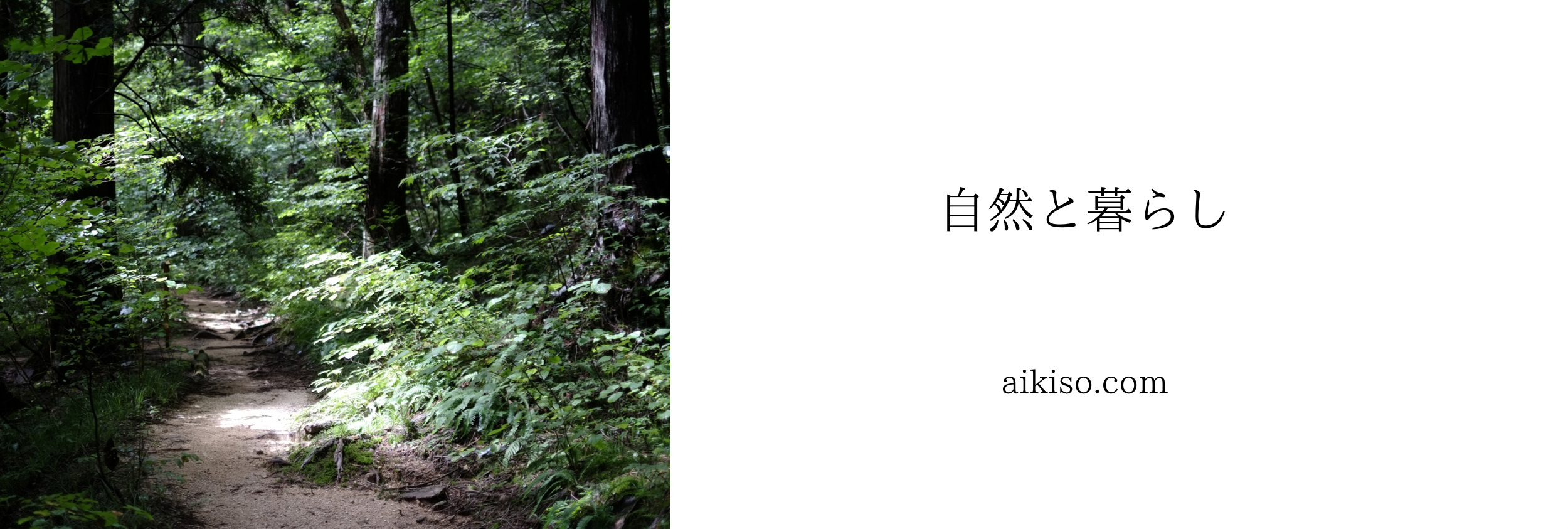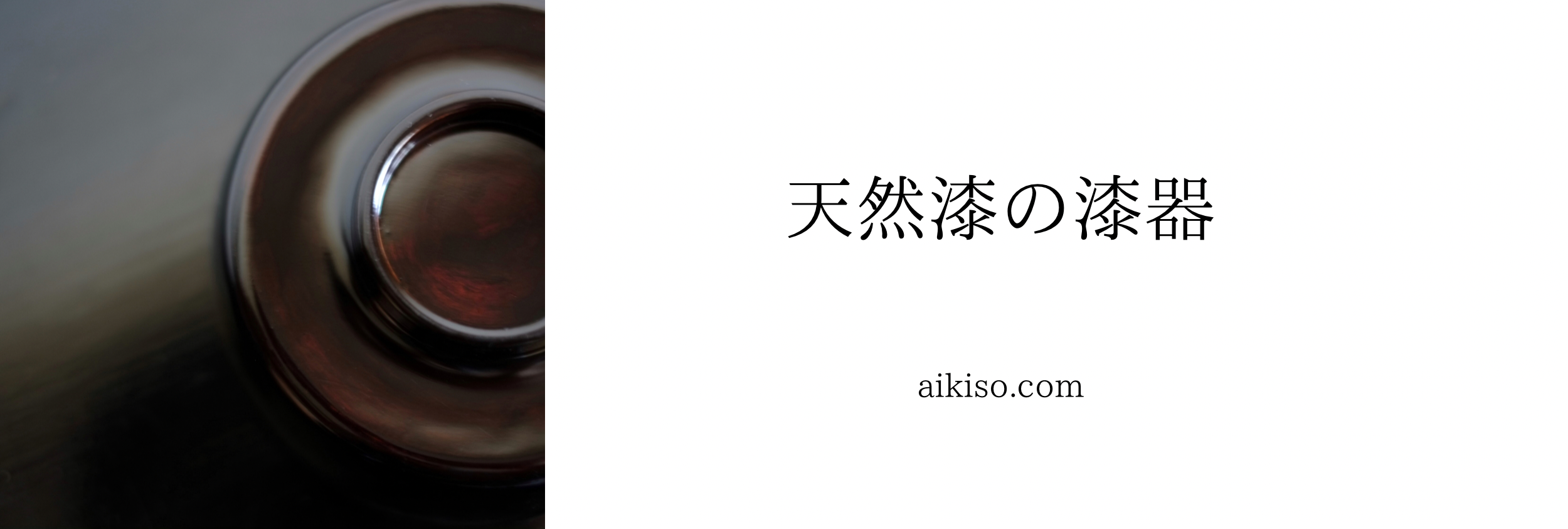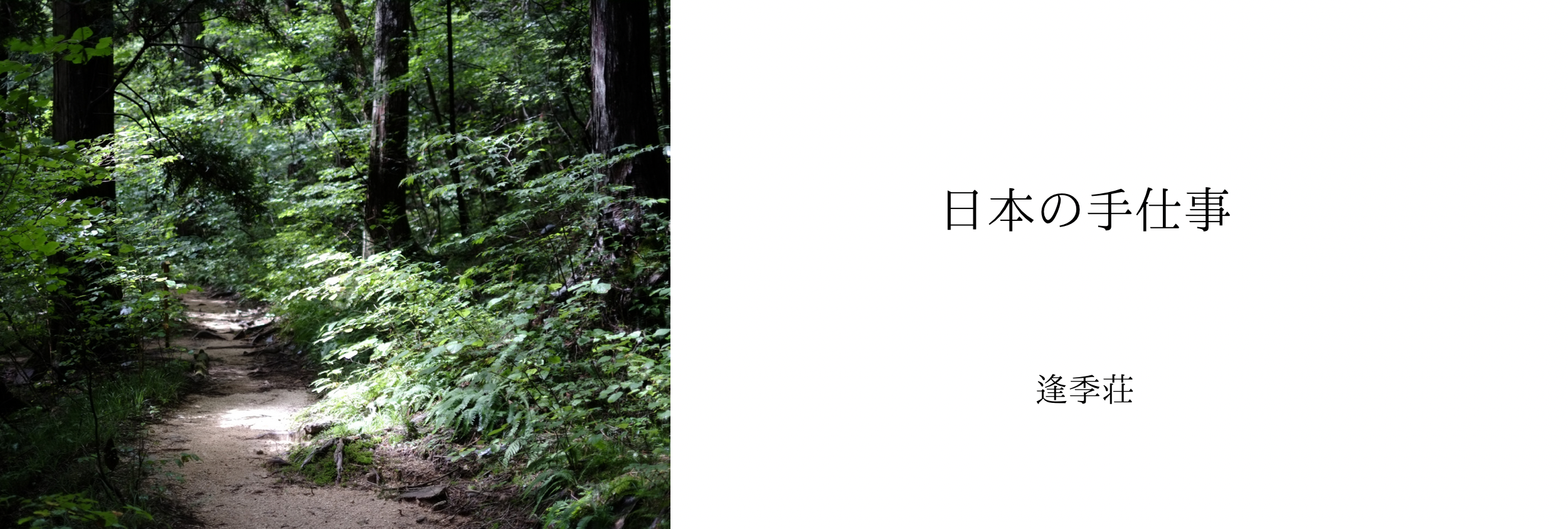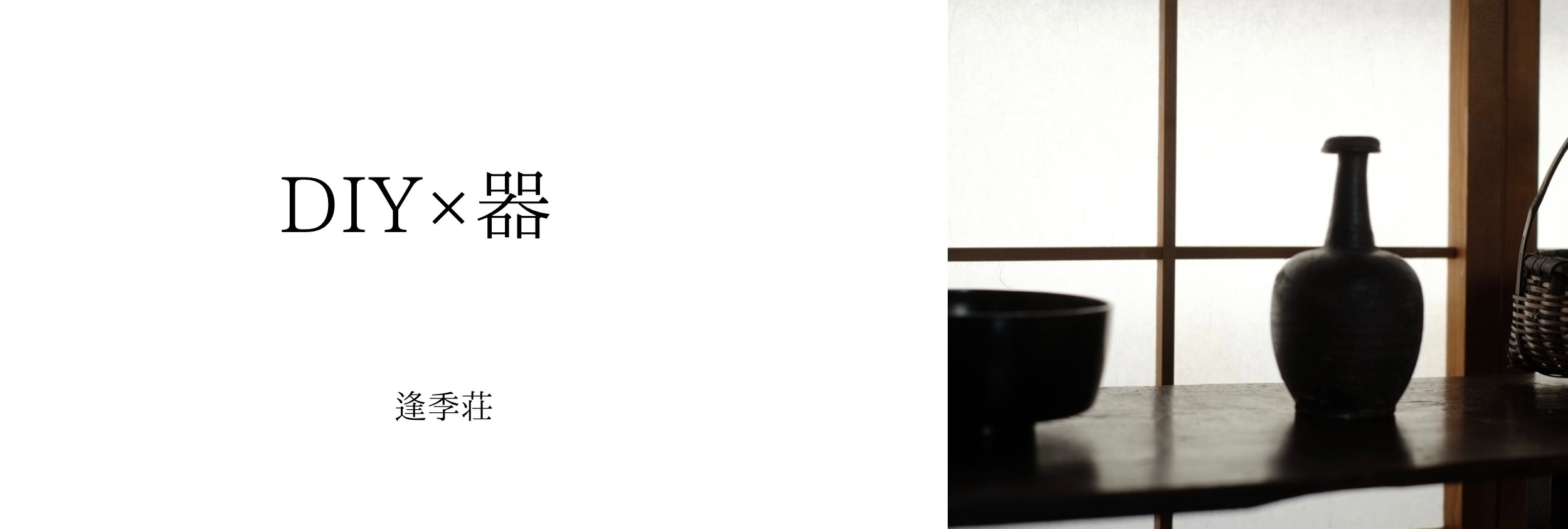DIYでの漆喰塗りの極意。左官コテよりも手塗りが一番早くて綺麗。
近頃、家の壁を日本の昔からある自然素材である漆喰仕上げにするのが流行っています。
しかしこの漆喰をDIYで塗っていこうと試みるとき初めてだとコテの使い方やどうやってうまく仕上げるのか不安が付きまとうと思います。
漆喰を施工できる下地について濡れる場所と濡れない場所があります。
漆喰を塗るまでの下地作りについてはこちらから
養生の方法と重要性
漆喰をすぐ塗りたくなる気持ちを抑えて、
まずはしっかり養生をしていきましょう。
養生はしっかりやろうとすると意外に手間がかかるのだが
ここで手を抜くと仕上がりも失敗して後悔する
結果になりかねない。
(養生の失敗した仕上がりの様子は後半に記述。)
特に木枠の部分は漆喰を吸うと灰汁が出て周りが黄ばんでしまう可能性が高く
養生をしっかりして綺麗に塗るところと塗らないところをきっちり覆わないと最終的な仕上がりのに多大な影響を及ぼすことに(しかし分かっていても面倒になってしまうのが養生なのです。)
養生テープの種類
養生テープは
幅50mmと25mm
のものの2種類を
場所によって使いわけて使用しました。
(意外に消費するので余裕を持って買っておきましょう。後で買い足す羽目に。。。)
今回床の養生に関しては
後々は土台を作り上げてフローリングを貼る為
現在の床は汚れても大丈夫な為
保護はしませんでしたが、
床を漆喰で汚したくない場合は床の養生も必須です。
(練り漆喰は柔らかいので床に落ちやすく白く固まってしまうと
綺麗に取り除くのに一苦労する。)
漆喰を塗る下地は??
・ビニールクロス
・コンクリート(の上に裏紙)
・ベニヤ板 (の上に裏紙、アクドメシーラーを二回塗った下地)
今回はこちらの3種類の下地に練り漆喰を塗ることになりました。
今回使用する漆喰
練り漆喰は最近ではホームセンターにも置いてある
うま〜くヌレールが一番有名でどころですが、
今回はうま〜くヌレールよりも価格が安く塗りやすさ、
仕上がりにも定評がある
ロイヤル通販者の練り漆喰
を使用した。

4kg ×5袋でこのように包装されて送られてきた。 ちりとりの使い方については後ほど説明。
練り漆喰と本漆喰について
練り漆喰のメリットは届いてそのまま開封すれば塗ることができるのと、
初心者でも簡単に壁紙の上からでも施工できるように
改良されている製品が多いのが特徴。
逆に本漆喰と呼ばれる昔から使われている漆喰は余分な材料が入ってなく
コストパフォーマンスの面でも断然お得だ。
ただし自ら水で溶いて塗りやすい固さに練らなくてはいけないので
別途、攪拌ミキサーは必須で
漆喰の塗りやすさについても左官コテを使って
しっかりとした下地作りが必要だ。
お手軽に作業の効率も考えて漆喰壁を楽しみたいのなら練り漆喰、
本格的な漆喰仕上げをしたいのなら本漆喰を選ぶといった感じだろうか。
今回は工期も考えて練り漆喰をセレクトしたが
今度は本漆喰と呼ばれる、昔からの漆喰の塗装にも挑戦してみたい。
塗りに使う道具
今回、漆喰を塗るに当たってこちらの二つの試してみた。
・漆喰塗りに良く使われる 左官コテ 180mm
・コテよりも塗りやすいと定評がある 地ベラ

右が良く漆喰塗りに使われる左官コテ。左が地ベラ。
そして前述のちりとりは
漆喰を塗る為にコテ板の変わりとして代用しました。
漆喰の塗り模様
漆喰はコテ使の使い方によって様々な模様の仕上げをすることが可能です。
今回は変に模様をつけずになるべくフラットに仕上げるのを
目標にしていきたいと思う。

コテを使っての模様付けの一例
出展:原田左官工業所
まずは地ベラを使っての塗りに挑戦。
厚みものっけやすく塗りやすい。
ただし寝かして塗ってもどうしても、
端の方で完全にフラットに仕上げるのは難しい模様。
次に、左官コテを使ってみる。
塗る際に寝かししまうと練り漆喰と壁が吸い付いてしまったり初心者には扱いが難しい。
さらに一回吸い付いてまうと、塗布したい漆喰も取ってしまい下地の裏紙が剥がれてしまったりも。(しかも鉄コテを使用したので、1日使用した後錆びてしまった。)
本格的な職人による漆喰塗りには左官コテが一般的ですが、
素人が綺麗に塗るなら地ベラの方が使いやすいでしょう。
また左官コテも用途によって様々な種類があり漆喰を塗るのであれば仕上げコテと呼ばれる厚みの薄いタイプか柔らかいプラスチック製のものが、良さそうです。今回試しに使用したのは中塗コテというのだったので塗りにくかった模様。
どちらにしよ裏紙の下地から漆喰を塗るのに左官コテは向かない印象を肌で感じました。
そしてこの練り漆喰は2度塗りが基本で、
1度目は下地が透けるくらいに薄めに塗るのがポイントとのこと。
手塗りが最強。
地ベラでは薄く伸ばすことができないので、
一度手に漆喰を持ってから手のひらで漆喰を伸ばしてみました。
早い、簡単、伸ばせる、端も塗りやすい。
手袋にのっけて手で伸ばすのが一番効率が良いのに気付きました。

手だと角の場所も塗りやすい。漆喰で手が荒れないために必ず手袋は着用必須。コツは手の指の跡がつかないようにきれいに広げること。
そこからはバケツに漆喰を入れてひたすら伸ばす作業。
コテみたいに、模様付けやきっちりきれいなフラットな面を出すことは出来ないが、
下手なコテ使いよりはよほどきれいに
仕上げれると感じた。
(十畳の部屋を一人で塗るのはかなり疲れる。)
一度塗りが終了後、壁を見てみるとやはり下地の裏紙がふやけて浮き上がってきた。
しかしシーラー作業の時のように乾けば浮きがもどると信じて後日に託す。
完全に乾かしてから後日2度目の塗りで仕上げる。
二回目の塗りの作業に入ります。漆喰を吸って浮いた下地は漆喰が固まったことにより浮きはなくなってました。こちらが仕上げになるので一度目より少し厚めに塗布し、
仕上げ塗りも手で塗ることに。

手塗りで仕上げた様子。なるべくフラットも目指したが手の跡が残る。それもまた趣のある仕上がりに。
今回使用した漆喰ですが、十畳用の壁で
5袋20kgの推奨でしたが結局もう5袋追加する羽目になりました。
口コミにも書かれているように多めに
見積もって用意するのが吉のよう。
やっとこさの思いで和室6畳と洋間の5畳に漆喰を塗りおわることができました。

漆喰塗り完成!!。作業時に漆喰が垂れ落ちて床がだいぶ汚れた。フローリングの場合はしっかり養生が必要。
そして塗り終わり完全に乾くのを待つ前に養生テープを剥がしていきます。完全に乾いてしまうと塗ったところも一緒に剥がしてしまう可能性があるとのこと。

ビリビリビリビリ剥がしていく。気持ち良さの快感に浸るとともに養生の甘さを思い知る。
今回壁紙の上から塗った場所はもちろん、コンクリートの下地、ベニヤにアク止めを塗った下地とも灰汁がでて黄ばむことはなく、まずまず納得できる仕上がりとなりました。
まとめ
・養生は、やはりサボらず丁寧にやろう。
・DIYで綺麗な仕上げを期待するのは難しいがそれもまたよし。
・下地はしっかり作って、(アク止めやパテ埋め)漆喰は余裕を持って用意しよう。
ここまででひとまず壁は完成を迎えました。
次回からは畳から無垢のフローリングの張り替えの作業に移っていきたいと思います。